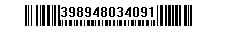
6月下旬のページ
6月30日
ホルモン
ホルモンの語源は、ギリシャ語の「刺激する、興奮させる」と言う言葉。其の名の通り、身体の組織や臓器を刺激する化学物質です。
ホルモンは、身体の特定の器官から作られる化学物質です。其の数は約40種類に上り、血液の流れに乗って、様々な組織や臓器に刺激を与え、情報を伝達する働きをして居る。
代謝や食事、性機能等、大切な生命活動のコントロールは、此のホルモンを介して行われる。ホルモンは、心身がバランス良く働く為の潤滑油として、無くては成ら無い重要な役割を担って居る。
ホルモンを作る器官を、「内分泌器官(内分泌腺)」と言う。脳の視床下部や下垂体、甲状腺、副腎、膵臓等の他、性腺(女性では卵巣、男性では精巣)が、此に当たる所です。
身体に取って大切なホルモンですが、分泌される量は極僅かです。其れが、少しでも多く成ったり、少無く成ったりするだけで、組織や臓器は正常に働か無く成る。
此のデリケートなホルモンをコントロールして居るのが、脳の「視床下部」と「下垂体」です。
視床下部は、血液中の有らゆるホルモンの分泌量を常にチェックし、異常が有れば、直ぐに正常に戻す指令を出す。此の指令を受けて実際に行動するのが、視床下部の直ぐ下に有る下垂体です。此うした視床下部と下垂体のコンビネーションに因って、私たちの身体の微妙なホルモン濃度は保たれて居る。
一般的に女性ホルモンと言われて居るのは、卵巣から分泌される「卵胞ホルモン(エストロジェン)」と「黄体ホルモン(プロジェステロン)」の2つですが、女性の身体に関係するホルモンは、他にも沢山有る。此等も全て、視床下部と下垂体に因ってコントロールされて居る。
女性ホルモンの働きは、
下垂体を刺激し、性腺刺激ホルモン(卵胞刺激ホルモン・黄体形成ホルモン)を放出させる。
性腺刺激ホルモンの一つ。卵巣に作用して、原始卵胞を成熟卵胞へと成長させる。
性腺刺激ホルモンの一つ。卵巣に作用して、成熟卵胞の排卵を促す。排卵後の卵胞を黄体に変えるは働きも有る。
乳腺に作用して、乳汁の分泌を促す。
副腎皮質に作用して、副腎皮質ホルモンの分泌を促す。
甲状腺に作用して、甲状腺ホルモンの分泌を促す。
人体の発育や成長を促進するホルモン。
メラニン細胞を刺激して、色素を沈着させる。妊娠すると乳首や小陰唇が黒ずむのは、此のホルモンの作用。
腎臓に作用し、尿量や体内の水分、血圧を調節。
出産時、子宮を収縮させて陣痛を起こす。乳房に作用して、乳汁の分泌を助ける。全身の筋肉の不随意運動にも関与して居る。
子宮に作用して、子宮内膜を増殖させる。思春期には、女性特有の第二次性徴を起こす。
子宮に作用して、子宮内膜から粘液を分泌させ、受精卵の着床と妊娠維持を促す。
男性ホルモン(テストステロン)は、
男性の精巣(睾丸)から分泌され、性器や体毛の発育、筋肉の発達、声の低音化等、男性の身体を作る働きをする。
所が、女性の体内でも、副腎皮質から少量の男性ホルモンが分泌されて居る。通常は、多量に分泌される女性ホルモンが、男性ホルモンの働きを抑えて居るが、女性ホルモンが十分に分泌され無いと、男性ホルモンの影響が表面化する事が有る。
女性ホルモンは女らしさを、男性ホルモンは男らしさを作る。ホルモン全体に言える事だが、狂わすのは乳製品を中心に動物性蛋白質で有る。狂った身体を再構築するのは種(米や木の実等)で有る。
「身体の浄化と回復」のビームライトバーコードと同時に使用されると効果的です。
女性ホルモンのビームライトバーコード(1999.6.30.UP)
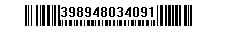
「身体の浄化と回復」のビームライトバーコードと同時に使用されると効果的です。
男性ホルモンのビームライトバーコード(1999.6.30.UP)
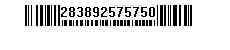
<ビームライトバーコードに関しての注意事項は3月17日を再度御読み下さい。>
6月29日
解熱
熱が出るが故に維持されて居る生命・・・・・・で有る。だから其の原因を把握する事が大事で有る。原則として炎症部位は冷やす事。
例えば、風邪熱の時(38℃以上)は胸部と腹部に聖士會館オイル(オリーブ油とか胡麻油で良い)を塗り、其の上にティッシュを1枚乗せ、其の上にアイスパックを熱が下がる迄乗せて置く。但し、39℃を越す様で有ったら加えて喉の周りにも同じ事をする。其れからパジャマ等の色は青色系で無いと熱が下がり難い。赤系の色は特に熱は下がり難い。
高熱の時に、胸部に汗を掻き始めたら塩気が足り無く成って来たのだから塩気を加えて遣る(梅醤番茶に大蒜を入れて)。特に食事は必要無い。何故ならばウイルスに力を与える事に成るからだ。回復時には、腸が弱って居る為にスープ→粥→普通の御飯と成る。兎に角匂い物(大蒜、韮、葱、玉葱等)を使用する。
1.冷やした胡瓜水を、盃一杯位飲ませる。何物にも敵する物の無い程の清涼感を与え
る物で、やがて熱が下がる。
2.薺全草を陰干しにして置き、其の煎じ汁を御茶代わりに飲用する。
3.赤砂糖と生姜汁を其其盃1杯ずつに、熱湯を大きな湯飲み茶碗一杯加えて飲み、布
団を被って寝て汗を出すと治る。
4.乾燥した木賊(トクサ)を煎じて飲む。
5.乾燥した浮草を煎じて飲む。
6.梅干しの黒焼きを粉にしてから、熱湯で内服する。
7.柿の若葉を適当に刻み、陰干しにして柿茶を作り、常用する。
8.河原蓬の花穂と種子を煎じて温服する。
9.梓木(キササゲ)の内皮を煎じて飲む。
10.枸杞の根皮を煎じて飲む。
11.枝下柳(シダレヤナギ)の葉を煎じて飲む。
12.西瓜の乾燥させた種子を、一日量5gを400㏄の水で半量に成る迄煎じて飲む。
13.杉菜茶を、御茶代わりに飲む。
14.薄(ススキ)の根を良く水洗いして乾燥させ、煎じて飲む。
15.芹の生の搾り汁を飲む。 ※小児の場合は、2〜4㏄位を1回に飲ませる。
16.露草の全草を煎じて飲む。
17.梨の果実を皮の侭輪切りにし、煎じて飲む。
18.棗の乾燥した果実を煎じて飲む。
19.包の木の乾燥した果実1〜2個砕き、煎じて飲む。
20.リラの葉又は樹皮を細断して乾燥させ、煎じて温服する。
21.烏瓜酒を飲む。
22.蒲公英の全草を、花が咳く前に堀り取って、天日で乾燥させて置き、必要な時、小
さく刻んで一日7〜8gずつを水一合で煎じて飲む。
23.豆腐パスタは氷の代用として、頭、首、胸、腹部、に湿布すると邪熱を速やかに吸
収するが、其の効は水や氷の比では無い。
24.夜中に急に子供が発熱した場合、鶏卵3個を白蜜一合の中に入れて良く掻き混ぜ、
此を飲ませると立ち所に熱が下がる。
25.仏手柑(ブンュカン)をスライスして飴色に成る迄煎じて飲む。臭い毒汗が体中から
噴き出して治る。
26.烏瓜酒を飲む。
27.蒲公英の全草を、花が咳く前に堀り取って、天日で乾燥させて置き、必要な時、小
さく刻んで一日7〜8gずつを水一合で煎じて飲む。
風邪の手当
風邪を引いた時は、出来るならば1回で治したい物。梅醤番茶に2片の大蒜を擂り卸した物を最後に混ぜてフーフー言って飲み、床に入ってゆっくり寝ると大概は朝迄には治って居る。序でに、部屋に殺菌性のハーブを漂わせて於くと尚良い。
喉の炎症には玉葱を剥いて、剥いた皮の凹形の方向を喉に当て、其の上に、玉葱の黄色い外皮を被せて包帯を巻き寝る。
究極の解熱には、蛞蝓を生の儘飲むと良い。
併用療法として、例え40℃の熱が有ったとしても風呂に入り(高熱の場合は水風呂に氷を入れて入ると良いが、出来無い人は極力冷たい風呂に入る)身体をすっきりさせると効果は加速する。身体が清潔な方が気分も良いし、新陳代謝を促す。
「身体の浄化と回復」のビームライトバーコードと同時に使用されると効果的です。
解熱のビームライトバーコード(1999.6.29.UP)
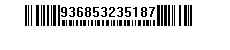
<ビームライトバーコードに関しての注意事項は3月17日を再度御読み下さい。>
6月27日
血液
動物体内を循環する体液の一種。脊椎動物では血球(赤血球・白血球・血小板)、及び、血漿から成る。組織に酸素・栄養・ホルモン・抗体を供給し、二酸化炭素其の他の代謝生成物を運び去る。白血球は食作用や抗体産生に因り、生体防御の役をする。
血は生命に取って最も大切な物だと言う事は、昔から理解されて居た。其れは、血判や血書と言う悲愴な言葉や、血税、血食、血祭り、血涙、血気、血族、血統、血筋等と言う言葉からも窺い知る事が出来る。最近では、国民全体が健康や病気に関心を持つ様に成ったので、血圧、血色、血清、或いは、出血、貧血、献血等、日常会話にも血に纏わる言葉が多く用いられる様に成った。
血液は血管外に出るとやがて固まる。此を血液凝固(凝血)と言う。普通は数分で固まって仕舞いゼリー状に成る。此の凝塊を血餅と言う。血中のフィブリノーゲン(繊維素原)がフィブリン(繊維素)と成り、其の綱目に赤血球や白血球等、有形成分が引っ掛かった物が血餅で有る。傷付いて出血した時、血が止まるのは、血管が収縮し修復される事と、血餅に因り傷口が塞がれる為で有る。そして、失血が塞がれる為で有る。そして、失血が塞がれ傷が治る。次いで、暫くすると固く成った血の塊が剥げ落ちる。
血液凝固の絡繰は可成り複雑で、幾つもの凝血因子(物質)が関与して居るが、現在12の因子が解って居る。此等の凝血因子が1つでも働か無いか、働きが弱いと血は固まり難いか固まら無い。其の点を利用して血液凝固を阻止し、輸血する事が出来る。ヘパリンやクエン酸ソーダと言う薬が其の血液凝固阻止剤で有る。此等の薬を血液に混ぜて暫く放って置くと、血液は固まらず、其の内に、透明な部分と赤い部分に分かれて来る。早く分離させたければ遠心沈殿器に掛ければ良い。透明な部分を血漿言う。下の赤い部分には、赤血球や白血球、血小板等が入って居る。血漿と血清の違いは、其処に繊維素原と言う凝固因子が在るかどうかに因る。
血液は体外に出ると数分間で固まるが、其の固まる時間の長引く病気が有る。此を血友病と言う。凝固因子が欠損した病気で有って遺伝する。そして、女性には少無く男性に多い。其の理由は性染色体に其の欠陥が有るからで有る。女性が媒介者と成る。但し、遺伝関係が全く証明され無い物が30〜40%も有ると言う。此は遺伝子に突然変異が起こったとしか考えられ無いと言われて居るが、此等には奇形と同様に食事や公害が絡んで居るのかも知れ無い。
血液は何故生体の血管内で凝固しないので有ろうか?1つにはヘパリンが存在するからだと言われて居る。又、凝固物質を溶かす物が有るからだ共言われて居る。此のヘパリンは、最初、肝臓(へパール=ラテン語)で見付かったので此の名が有る。此の反対に、生体の血管内でも血液が固まる場合が有る。此を血栓(血栓症)と言う。血管の内面の損傷や炎症、或いは、血流の変化に因って出来る。従って、動脈硬化症やリュウマチ性心内膜炎の患者、或いは手術等に因って高度な安静状態で仰臥して居る患者に起こり易く、血液が濃い程起こり易い。血栓が出来ると、血管腔が狭く成るか、塞がれる。そう成れば、其れ因り末梢へ血流が阻害され、支配下組織の機能が落ちるか死ぬ。組織が体内で死ぬ(腐る)事を壊死と言う。
血栓が血管壁を離れて血流と共に移動し、其れが因り末梢の血管に引っ掛かる場合が有る。此を塞栓症と言う。其れが脳の血管や心臓の冠状血管に引っ掛かると大変で有る。塞栓症を起こす物を栓子と言う。脂肪、空気、炭粉、腫瘍細胞、寄生虫、寄生虫卵等多数有る。例えば、空気を静脈内に注射すれば、心臓を通り肺の毛細血管に引っ掛かり、呼吸困難で死亡する。
血管を運河に例えると、血漿は其処を流れる水、血球は船に相当する。即ち、血液は血球と血漿で出来て居り、どちらも物質を輸送するが、血球は運河を行く船の役目をする。血液も、又、1つの臓器で有って、血球の内、赤血球は固有細胞、白血球は支持細胞、そして、血漿は組織液と言う事が出来る。其の意味では輸血も1つの臓器移植で有る。唯、血液と言う臓器の特異な事は、液状で有る事で有って、身体の中では血液とリンパの他は全て固体、又は、半固体で有る。但し、血液だけが水っぽいのでは無い。血液の80%は水で有るが、形を成した腎臓も、又、同じ位の水を含んで居る。脳の灰白質に至っては85%が水分で有る。因みに、骨の硬い部分は25%、脂肪組織に至っては、20%の水分しか含んで居無い。そして、身体全体では60%が水で有る。勿論、老若男女に因って可成り差は有る。
血液が大量に失われると死亡する。では、出血多量だと何故死亡するのか?其れは、血圧が下がり、脳や心臓と言う重要な臓器へ血液が流れ込ま無く成り、ショック状態に陥るからで有る。其の他、血中成分の減少も原因して居る。推算する所に因ると、血液は体重の1/13(女性7%、男性8%)程で有るが、男は女因りも血の気が多い。普通の体格の男子には4.5〜5.0l(一升瓶約3本)の血液が有り、女子では3.0〜3.5l有る。其の内、1/3が失われると死亡する。然し、一日掛かりで、ゆっくり出血した場合ならば半分でも助かる。出血は外傷に因るのが普通だが、外科的手術に因って失血する事も多く成った。其の場合には輸血が行われる。其れに必要な血液は献血に因って賄われて居る。献じられた血液は血液銀行で保管され、必要に応じて引き出して使われる様に成って居る。
献血時に1人から1回に200〜400ml採血する。但し、献血には、16歳〜65歳と言う制限と、体重が男性で45㎏、女性で40㎏以上で健康者と言う条件が付けらてれ居る。最近は、全血を採取するのでは無く、成分献血と言って血漿のみを採取する方法も取られて居る。こうすれば献血者の負担が少無い。献血に際し、血液の比重が軽い為、血が薄い為に不合格の烙印を押される者が1割以上も居る。不合格に成った人の多くは女性で有り、食生活に欠陥が有る。問診に因ると甘い物が好き、コーヒー、紅茶の飲み過ぎ、白パンや白米の過食で有る。殆ど、精白食品、加工食品等に頼って居る。此の過ちを正すには、玄米菜食に緑黄野菜、木の実、海藻類、豆類、胡麻を基本食とするしか無い。
赤血球
普通、輪形では無く円形のドーナツ型をして居り、其の直径は約7〜8μmで、1㎝四方に14,000個も並べられる位小さい。其の赤血球を辛い食塩水の中に入れると、縮んで金平糖の様に成る。そして、反対に真水や薄い食塩水に入れると膨らんで、ついには赤血球膜が破れて仕舞う。此の丁度中間で、最も都合の良い食塩水に入れると、赤血球は正常の形の儘で有る。此の食塩水の濃度は、0.9%で、傷口に付けても、目に入れても痛く無く「生理食塩水」と言う。そして、「リンゲル液」とは、カリウムやカルシウム、マグネシウム等を血漿の其れに似せて作られた物で有る。生理食塩水は血漿と同じ浸透圧を持って居る。浸透圧とは食卓の塩や砂糖が水を引き付ける様な物で有る。溶けて居る物が何で有ろうと濃い液(分子の数の多い液)は浸透圧が高い。0.9%以下の食塩水に赤血球を入れると膨らみ、ついに赤血球膜が破れる時、赤血球の中の蛋白質が外に出て仕舞う。此の現象を溶血と言う。此の蛋白質は血色素(ヘモグロビン)と言われ、赤い血潮の素で有る。溶血は此の他、黴菌の毒素やアルコール、石鹸、中性洗剤等でも起きる。
血色素は、酸素と早い速度で結び付く性質を持って居り、条件が変わると、又、簡単に離れる。即ち酸素の多い所に行けば酸素と結び付き、薄い所に行けば離れるので有る。即ち、血色素にそうした性質が有る為に、赤血球は酸素を運ぶ事が出来るので有って、言わば、赤血球は酸素を運ぶヘモグロビンと呼ぶコンテナーを積んだ船で有る。もし血液中に此のヘモグロビンが無いと1/70しか酸素を運ぶ事が出来無いので有る。
此のヘモグロビンと、酸素因りも因り強く結び付く物に一酸化炭素が有る。一酸化炭素は酸素因りも250倍も強い力でヘモグロビンと結び付き、赤血球から酸素を追い出して仕舞う。其れが為に都市ガスに因って窒息死するので有る。
赤血球は1㎜立方の血中に成人男子で500万個、女子で450万個も含まれて居る。此の量は滴の血の中に、日本の全人口の数倍にも及ぶ数の赤血球が入って居る計算に成る。
貧血とは、一般的に単位容積当たりの赤血球が減少した物を言うが、数は正常でも1個当たりのヘモグロビン量が少無い貧血も有る。又、1㎜立方当たりの赤血球数も、其の中のヘモグロビン量も正常だが、大量出血で全体の血液量が失われた貧血、又は、鉄分の不足に因る鉄欠乏性貧血と言うのも有る。ヘモグロビンが、酸素と実際結び付くのは、其の中の鉄分子だからで有る。
白血球
赤血球と白血球の大部分は骨髄で作られて居る。そして、其の生産高は、白血球の方が3:1で多い。だが、流血中の赤血球と白血球の比率は500:1で断然赤血球の方が多い。白血球は1㎜立方の血液中に6,000〜7,000個。多くても10,000個位しか無い(正常範囲は4,000〜10,000個)。そして、全身で300〜400億しか無い。此の理由は、白血球の寿命が短いからで有る。赤血球は約4ヶ月間の寿命が有るのに対し、白血球の寿命は2〜4日、或いは、白血球の種類に因って異成るが、2週間位共言われて居る。
白血球の数は厳密に言うと個人差ばかりでは無く、同一人でも色々な条件で変わる。例えば、肉食すると多く成る。従って、アメリカ人の方が日本人因りも一般に多い。そして、午後には増加し、筋肉労働や食事の後にも増え、又、妊娠や出産で増え、細菌の感染に因っても増える。
赤い血、白い血と俗に言われる様に、赤血球と白血球の違いは、其処に赤い色素が有るかどうかと言う事も有るが、両者のもう一つの大きな差は、赤血球には全く自動性が無いのに対し、白血球はアミーバの様に自分で動き回る事が出来ると言う点で有る。そして、赤血球には核が無く、白血球には核が有る。又、核だけでは無く、色素(中性、酸性、塩基性)に染まり易い粒子(顆粒)が在る。そして、白血球は、好中球、好酸球、好塩基球と単球、リンパ球(大、小)に分類されて居る。此の内、好中球が最も多く、中性色素に良く染まり、動きも活発で(20秒間に1㎜程度)移動する事が出来、黴菌や壊れた細胞片を取り込み、分解処理して仕舞う。此の様な細菌を食細胞と言う。単球も其の1つで有る。此の単球は血管外に出て変形し、大食球と成る。そして、更に、大食球は警官に例えると、移動型(パトロール型)と定着型(駐在型)に分かれるが、従来は細網内皮形と呼ばれて居た物で、リンパ組織、肝臓、脾臓等に多く見られる。但し、此の好中球の食菌能力は甘い物を食べると極端に落ち込み、黴菌の感染を受け易く成る。此の白血球の食菌作用はビタミンCに因って促進される。好酸球は寄生虫病、気管支喘息等のアレルギー性疾患の際に増加し、好塩基球はアレルギー性反応物質を放出する事で知られて居る。
白血病とは、血球を作る組織の腫瘍で有って、急性と慢性に区別されるが、急性型が増えて居る。癌の原因は可成り複雑で有る。白血病は乳癌や子宮癌、腸癌等と共に高脂肪食を好む人に多い。
血液とリンパ液
我々の体重の約6%を占める血液は、正に驚くべき液体で有る。血液には、莫大な数の赤血球(人の血液は正常な状態では、500万個/1㎜囟の赤血球を含んで居る)、及び、小さな、自ら運動する事の出来る沢山の白血球が含まれて居り、此等は全て、塩類、糖、蛋白性の物質の濃い水溶液(血漿)の中に漂って居る。
赤血球は肺の中で極めて速やかに、事実上其の容量一杯に酸素を取り込み、酸素を必要とする細胞の在る場所で、其の全部或いは一部を放出して、身体の中で欠く事の出来無い重要な役割を果たして居る。此の様に細胞から肺へ帰って来る時には、赤血球は活動の結果生じた老廃物の1つ、炭酸ガスを運搬する仕事に参加する。炭酸ガスは熱を生み出す酸化作用の結果生ずる物で有り、酸化作用は生体の機能の中で力学的な仕事に欠く事の出来無い物で有る。自分で運動する白血球は体内の反応性に乏しい異物や侵入した細菌を取り除き、身体を守る役を果たして居る。若しも、異物や細菌を溜まるに任せて於けば、流れは汚れ、不潔に成って仕舞うだろう。
血漿は血液の半分以上の体積を占めて居り、腸管の消化作用の最後の過程で作り出されたあらゆる類の栄養物を運搬するコンベアで有る。此の様な栄養物は、酸素と同様、生物の身体のあらゆる場所に運ばれて、全ての細胞に、どんなに奥まった片隅に在る物へも然るべく行き渡り、必要が無ければ身体の特定の器官に運ばれて、将来に備えて蓄えられる。
血漿のもう1つの機能は、身体の至る所に在る細胞から、身体の機構が働いて生じた炭酸ガス以外の老廃物を運び去り、腎臓へ届けて、其処から排出させる事で有る。
血漿は傷を受けた部分に触れると、液体からゼリー状に変化する(凝血する、或いは凝固する)驚くべき能力を有して居る。例えば、血管が傷付けられたり、切られたりして、開いた傷口から血液が失われる恐れが有る時には、血漿のゼリー化、即ち凝固が起こって栓を作り、遅かれ早かれ傷口を塞いで仕舞う。若しも、此の作用が無ければ、生命を危険に晒す様な酷い出血が起こる所で有る。
リンパ液が血液と異成って居るのは、主に、其れが血球を含まず、蛋白質の含量も血漿程には多く無い点で有る。然し、白血球は持って居るし、糖も塩類も含んで居る。又、凝固もしうるが、リンパ液の凝固した物は、血液其の物が普通に凝固して出来るゼリー状の物因り柔らかい。
リンパ液、或いは、組織液は、血管と組織の細胞の間に広がって居り、細胞と流れる血液との間で互いに交換される物質は全てリンパ液の中を通り抜けて行く。詰まり、リンパ液は其の様な交換の直接の仲介者なので有る。
血液とリンパ液の違いは、偶々、何かにぶつかったり、挟まれた時に、皮膚の一番表面の層だけが傷付いて、リンパ液で満たされた「水膨れ」が出来る。皮膚のもっと深い部分が傷付けば、血管が破れて、流れ出た血液が「血豆」を作る。
血液の酸性とアルカリ性
筋肉が働けば、同時に乳酸と炭酸ガス(水に溶けて炭酸に成る)が必ず生ずる。同じ様に蛋白質の多い食物に含まれて居る燐や硫黄が酸化されて、燐酸や硫酸が身体の中で作られて居る。病気の症状に因っては、更に性質の異成った酸性の物質が現れる。
一方ナトリウム、カリウム、及び、カルシウムの様な塩基が、特に野菜に多く含まれて、身体に取り入れられ、又、酸は、酸性の胃液として分泌され、一時的に身体から出て行くで有ろう。こうして、血液をアルカリ性にする様な条件が生み出される。血液が酸性、アルカリ性の何れの方にも目立って変化しないと言う事は、細胞が生存し、正しく作用を営む為に最も大切な事で有る。
血液が「何性」で有るかは、血漿の水素(H)イオンの濃度で決められる。水素イオンは、水素と言う元素の原子が電荷を帯びた物で有る(原子が電子を失ったり、余分に得たりすると、其其+、又は、−の「電気」を帯びる。水素が電子を1個失って、+の「電気」を帯びた物が水素イオンで有る)。
塩酸(HCl)を水に加えると、HCl
が分解、或いは、別な言い方をすれば解離して、成分イオン、即ち、水素イオンと塩基イオンに成る。
酸性の程度は、溶液中に有る水素イオンの数で決める。同じ様に水溶液のアルカリ性の度合いは、水素(H)と酸素(O)2つの元素が結合して出来た物が電荷を帯びた、所謂水酸化物イオン(OH)の濃度で決められる。
純粋の蒸留水(H堄O)は、僅かに Hイオンと OHイオンに解離して居るが、此等のイオンの数は当然御互いに等しい。純粋な蒸留水は中性で有ると考えられるが、其れは酸性に働く物や、アルカリ性に働く物が存在しないからでは無く、両方が同じ程度に有るから中性なので有る。
摂氏22度の純粋の水には、1,000万lに付き、重さにして1gの水素イオンが含まれて居る。言い換えれば、水素イオン濃度は、1/1,000万分、或いは、1/10𡈁、或いは、10‐𡈁で有る(イオン等の濃度は、普通「モル濃度」即ち、1lの溶液中に溶けて居る物質の「モル数」で示される。1モルの水素イオンは、約1gで有るから、今の場合、水素イオン濃度は「10‐𡈁」モル濃度と言う事に成る)。
純粋な水の水素イオン濃度も、矢張り10‐𡈁(モル濃度)で有る。実際、負の指数の積は、どの様な水の溶液でも、常に−14で有る事が知られる(H+とOH-のイオン濃度の積(イオン積共言う)が常に10-囅囨に成り、「積の指数」が常に−14に成る)。現在では、此の様な負の指数を用いるのを避けて、中性をpH=7と表示して表す習慣に成って居る。若しも、水素イオン濃度が10-囷で有れば、水酸化物イオンの濃度は10-圕で、此の液は酸性で有る。逆の関係に成れば、勿論其の液はアルカリ性で有る。詰まり、水素イオン(H)の濃度を表す指数がpH7因り少無ければ、水酸化物イオン(OH)が優勢で、其の溶液は酸性で有る。一方、若しもpH7因りも大きければ、水素イオン(H)が過剰でアルカリ性に成る。
「身体の浄化と回復」のビームライトバーコードと同時に使用されると効果的です。
血液浄化のビームライトバーコード(1999.8.26.UP)
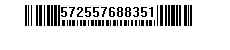
<ビームライトバーコードに関しての注意事項は3月17日を再度御読み下さい。>
6月26日
伸長
脳下垂体
一寸法師や親指姫に纏わる愉しい物語は、幼き日の夢を誘い出してくれるに充分で有る。
世界一小さかった人はポーリン−マスターズと言うオランダ女性で有る。19歳で死んだ時、59㎝しか無く、体重は3.4〜4.1㎏の間を上下した。但し、肥満体だったと言う。反対に大きい人は、ロバート−P−ワドロウで、アメリカのイリノイ州エールントンの生まれ。身長275㎝、足の大きさだけで45.7㎝も有ったと言う。然し彼は32歳で死んだ。日本には、江戸時代の興行力士に、生月鯨太左衛門(イケヅキゲイタザエモン=天保〜弘化)は235㎝有ったと言う。何故、此の様な差が出来るのだろうか。其れは下垂体で作られる成長ホルモンの分泌量に因る事が解って居る。
子供の内に、成長ホルモンの分泌力が弱まると、「小人症」に成る。此の小人症は、いわゆる「下垂体性小人症」と言って「甲状腺小人症(クレチン病)」とは違い、知能は全く正常で有る。「巨人症」は成長ホルモンの分泌過剰に因るが、大抵は下垂体の腫瘍が原因で有る。唯、思春期以後にホルモンの分泌が過剰に成ると言って、耳朶や、頬、頤と言う、出っ張った所が特に膨らむ。そして指は三味線等の弦を引き鳴らす撥の格好に成る。然し、実際プロレスラーや力士の様な彼の巨大な身体は、成長ホルモンの過剰だけでは出来上がら無い。そして、彼らの全てが、いわゆる下垂体の腫瘍に因る物では無い。
成長ホルモンは全身に直接作用する所の物では無いので、少し不完全な名称なので有る。と言うのは、肝臓や腎臓を刺激するホルモンで在る事が解って来た。即ち成長ホルモンは内臓刺激ホルモンなので有る。其の刺激に因って肝臓や腎臓からは、ソマトメジンと言うホルモンが分泌され、此が骨を成長させたり、蛋白質の合成を盛んにさせたりして、全身の成長を促す事が判明した。此の成長ホルモンの例でも解る様に、下垂体前葉は、甲状腺とか副腎皮質、性腺と言う支店をコントロールする銀行の本店の様な物で有って、現在の金融機構の様に、日本銀行と言う総元締めに当たる視床下部に因って更に上位から調整されて居る。即ち、視床下部に有るホルモン本部からは、各刺激ホルモンをリモートコントロールする「腺刺激ホルモン放出ホルモン」が分泌されて居る。成長に付いて言えば、成長ホルモン放出ホルモンで有り、性に付いて言えば、性腺刺激ホルモン放出ホルモンで有る。
生体内の生理学的機能に付いては、大抵二重の支配を受けて居るが、成長に関しては成長ホルモンの分泌を放出するホルモンの他に阻害するホルモンも視床下部で見付かって居る。此を成長ホルモン阻止ホルモンと言う。従って理論的には、此のホルモンの分泌異常でも「巨人」や「小人」に成る。此の他、下垂体性では無いが、頭や尻が大きく、手足の短い「軟骨骨異栄養症(軟骨骨発育不全症)」や家庭内不和や子供への無関心さから来る「愛情遮断性小人症」等が有る。
「身体の浄化と回復」のビームライトバーコードと同時に使用されると効果的です。
伸長のビームライトバーコード(1999.6.26.UP)
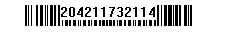
<ビームライトバーコードに関しての注意事項は3月17日を再度御読み下さい。>
6月25日
美肌
赤ちゃんの様な肌は戻っては来ないが、誰しも羨ましい肌で有る事は確かで有る。赤ちゃんの肌は潤って居るので有る。此の潤いとは、瑞々しい・・・・・・要するに水気に富んで居る。
肌荒れ
美しさと若さの秘密は、精神と身体の健康を保つ事で常に若々しい気持ちを失わず、心に蟠りの無い明るい生活をしたいもので有る。どんな時でも「もう年だから」と言う言葉は禁句で有る。知らず知らずの内に気持ちの上で老け込んでしまう。正しい食事と、適度な運動と、適度な休養と睡眠を取る事で有る。
美肌と食事には密接な関係に有る。
1.蛋白質、脂肪、糖質、ミネラル、ビタミン類のバランスが取れた食事で有る事。
2.皮膚、毛、爪等の主成分に成る蛋白質を摂る事。
3.カルシウムを摂る事。
4.糖分の過剰摂取は避ける事。
5.野菜、海藻等のアルカリ性食品を十分摂る事。
6.便秘をしない様、整腸作用の有る繊維質の物を十分摂る事。便秘は皮膚にも良く無い。
漢方では昔から美肌剤と言って、肌の色を白くし滑らかにする、桂枝茯苓丸は、冷え、逆上せ、便秘、月経痛、月経不順、不妊症を治し、古血を取って黒ずんだ肌を白くする。よく苡仁(ヨクイニン)は皮膚を滑らかにし、疣を取り、腫れ物や吹き出物を治す効果が有る。
皮膚の状態は体の鏡と言われて居るが、健康で在る事が、肌を守る大切な条件で有る。胃腸の弱い人は、胃腸の働きを良くするだけで肌が美しく成る。冷え性、肩凝り、便秘、月経困難が有る場合にも、其れ等を治すだけでも肌が美しく成る。
漢方薬には、
1.当帰芍薬散=最も良く使われる漢方薬で、冷え性で頻尿、疲れ易く、貧血気味で、月経不順が在る人に広く使える。よく苡仁を併用すると一層美肌効果が有る。
長期に服用する場合は、胃腸障害を防ぐ為に安中散とか六君子湯を併用すると良い。又、小柴胡湯を併用する場合も有る。冷え性で、冷たい物が食べられず、温かい物を好み、特に甘い物を食べたく成る人には、補中益気湯を併用する。
2.桂枝茯苓丸=冷え逆上せ、便秘が有って割合に体力の有る人に合う。よく苡仁を併用すると良く、長期服用には小柴胡湯等を併用する。
3.大黄牡丹皮湯=十分体力が有り、便秘がちで、月経障害が有って、盲腸の部位を押すと痛み、化粧が乗り難いと言う様な人に効果が有る。
4.麻杏よく甘湯=割合に体力が有って、鮫肌で肌がカサカサし、疣が出来易く、手足が荒れて、顔に雲脂の多い人に効く。
ダンディライオン(Dandelion) 和名=西洋蒲公英 キク科。
菊に似た黄色い花。冬の葉の様子は、薔薇の花をも思わせ「ロゼット」と呼ばれる。野生の物を庭に移植するのが簡単。毎年植え替えると育つ。
ギザギザに尖った葉の形がライオン(lion)の(de)歯(dan)の様だ、と言うのがダンディライオンの名の由来。日本では雑草と言うイメージが有るが、花が開く前に採取された葉は、蒲公英(ほこうえい)として漢方薬に使われて居るし、ヨーロッパ、特にイギリスやフランスでは、花はワイン、葉はサラダ用の春野菜、根は珈琲代わりとして愛されて居る。
根や葉には苦味が有るが、胃腸の機能促進や利尿効果、浄血作用が有る。葉は炒めたり、天麩羅や御浸しにも向いて居る。
【利用部位と薬効】
葉、花、根の全草にビタミンA・B・C、鉄分、カリウムを豊富に含み、健胃、利尿、暖下、強壮、胆汁の分泌促進、そして、美肌作りに効果が有る。
【症状別処方】
<夏ばて回復>
ドライのダンディライオン20gを袋に入れ、口を縛って風呂に入れる。給湯式の風呂の場合は、鍋に入れた500㏄の水で10分以上煮出し、其の抽出液を湯船に入れる。疲労を回復し、美肌を作る。
<血液浄化作用>
長期間飲み続ければ健胃作用が有る。アルカリ性なので、血液を浄化する働きも有る。蒲公英の根で作った茶は、色や苦味は珈琲そっくりなので、蒲公英珈琲と呼ばれる。
根を掘り、良く洗ってから細かく切る。此を天日で約半分の大きさに成る迄乾燥させ、焦げ茶色に成る迄弱火で気長に乾煎りする。1人分は小匙1杯とし、珈琲豆の時と同じ様に熱湯を注いで5分間蒸らし抽出する。
<強壮>
強壮作用が有るので虚弱体質の人に、太陽の力を得られる蒲公英酒。
乾燥根を容器の1〜3割の量を用意する。35°のホワイトリカーに此を10日間漬け込み、蒲公英を取り出し、酒を濾す。新しい容器に移し、更に3ヶ月間熟成する。
椎茸酢
【効用】
天日干し椎茸にはフィストテリンと言う成分が含まれて居り、コレステロールの付着を防ぐ。又、エリタデニン、ビタミンB12も含まれ、此等の成分はコレステロール値を下げる働きをし、ビタミンDはカルシウムの吸収を促進し、ビタミンB12は美肌に効果的で有る。
酢には、クエン酸、酢酸が含まれて居るが、クエン酸は疲れを解消し、体力を促進し、ストレスや肩凝りを解消し、副腎皮質ホルモンの生成を促進し、肌を引き締め、更年期障害や婦人病等にも効果的で有る。又、カルシウムの吸収を促進する働きが有るので、骨粗鬆症の予防に有効で有る。
【作り方】
天日干し椎茸10〜13枚をサーッと水洗いして、広口ガラス瓶に入れ、米酢を注ぐ。此の儘冷暗所に置き、10日から二週間程漬け込んで置く。
椎茸は必ず天日干しの物を使用し、酢は米酢、黒酢を使用し天然原料の物で無ければ効果は期待出来無い。
【用い方】
1回に盃1杯位を一日に数回飲むと良い。其の儘では飲み難いので水で4倍程度に薄め、檸檬汁を加えると飲み易い。水で薄めても飲み難い時には和風ドレッシングにしたり、菠薐草の御浸しや焼きそば、ラーメン等に掛けて食べると良い。又、白菜を熱湯でしんなりする程度に茹で、椎茸酢に浸けたり、公魚や小鰺を油で揚げてマリネにしたりして料理に応用する。
糠油
【効用】
美肌、脱毛症、白髪予防、田虫等の皮膚病。
【作り方】
大きめの丼の上に和紙を貼り、周りをセロテープで止めて、ずれ無い様に固定する。和紙は障子紙等の丈夫な物を利用する。
和紙の上に炒って居無い生の米糠を1掴み(大匙2〜3杯)乗せ、上に良く起こった炭火を静かに乗せる。其の儘置いて置くと、丼の中に糠の油が落ちて来る。炭火は、和紙が破れ無い内に取り除く。
1枚の和紙で、2〜3回繰り返して使える。障子紙等を使う時には、レーヨンやビニロン等を使う。
【用い方】
少量を患部に付け、指先で静かに擦り付ける。脱毛症の予防や治療には、洗髪する前に地肌に良く擦り込んでマッサージし、暫く其の儘にしてから洗う。因り効果的に使用するには、糠油と消毒用のアルコールとを半々に混ぜて使う。田虫や皮膚病には、一日に3〜4回塗り付ける。
鳩麦茶
使用部位=実。
薬効=疲労回復、滋養強壮、鎮痛、神経痛、利尿、消炎、疣、染み、雀斑、美肌、排膿、口内炎、歯茎の炎症。
飲み方=煎じる。
鳩が其の実を食べる事から、此の名が付けられた。イネ科の一年草の鳩麦の実を脱穀した物をヨクイニンと呼んで漢方として使う。褐色の皮を取った物を白様と言い、色の白い大粒の物が良品とされて居る。
成分には澱粉、蛋白質、脂肪が含まれて居るので、新陳代謝を良くして、疲労回復、滋養強壮に薬効が有る。其の他カンペステロール、スティグマステロールが含まれて居る。微量ながら抗腫瘍性物質のコイキセノライドも含まれて居り排膿、利尿、消炎作用が有るから、口内炎や歯茎の炎症に効果が有る。又、鎮痛作用も有り、神経痛にも効果が有る。
10月頃に実を採取し、果皮や種皮を取り除いて天日で良く乾燥させる。其の後弱火でゆっくり煎って御茶にする。
御茶にするには殻付きの儘か、殻を取った物どちらでも構わ無い。焦げ無い様に弱火でゆっくりと煎り、湿気ら無い様に保存する。10〜15gを800ccの水で半量に成る迄
煎じ、一日分として数回に分けて飲む。
新陳代謝を促進するので、肌を整える効果が有る。又、鎮痛効果も期待出来る。
胡瓜
ウリ科の一年生の蔓草
果実は完熟すると黄色く成る。黄瓜(キウリ)と呼ばれるのは此の為で有る。食用にして居るのは未熟な若い果実で有る。
長所
①栄養学上其程メリットの有る野菜では無いが、生で食べられ、瑞々しい。漬け物にしても、酢の物にしても美味しい。
②カリウムがナトリウムに比べて100倍多いので、高血圧の予防に良く、利尿作用も有る。
糸瓜と同様、熟した胡瓜の茎を地面から50㎝位の所で切り、其の切り口を瓶の中に差し込んで置くと、一夜の内に、胡瓜水が4合位採れる。浮腫の来る病気には、此を飲むと効く。汗疹、火傷にも胡瓜水、又は、胡瓜の絞り汁が良い。又、胡瓜水は美肌・面皰・雀斑に良い。糸瓜水因り上質で有る。
③漢方では小児の熱性下痢に良いと言われ、清熱解渇、利尿、消腫の効果が有るとして居る。
④ビタミン類は少無いが、ビタミンCは比較的多く、カロチンも有る。
⑤胡瓜は緑黄色野菜には入ら無いが、ビタミンCやカロチンの癌抑制作用以外に、癌抑制物質(テルペン・フェノール・ステロール)が含まれて居る。真っ直ぐな物因り曲がった物に多い。
短所
①身体を冷やす性質が有る為、冷え症の人や胃腸の弱い人は食べ過ぎては行け無い。唯、此の性質の為に利尿作用が有ると考えられる。
②カロチンやビタミンC以外のビタミンは非常に少無い。鉄分も少無い。しかし、亜鉛は多少有る。
③食物繊維が少無い。
ハイビスカス茶
使用部位=花。
薬効=便秘、血液浄化、美肌。
飲み方=浸出。
南国の花ハイビスカスは。其の鮮やかさでは正に夏の花と言えます。真紅の花は、アオイ科のフヨウ属の植物で、ハイビスカスと言うのは其の属名です。
此の真紅の花弁を原料にしたハーブティで、御茶の色も鮮やかなのが特徴です。其れと独特な酸味も此の御茶ならでは、と言った所です。
成分には、クエン酸、マロン酸、ビタミンCが主な物です。ですから、先ず疲れた時等に飲むと効果が有る。又、便秘、血液浄化等の作用が有り、結果として肌を整え、美しくする等の効果も期待出来る。
花弁を日陰干しにして乾燥させる。
飲む時には、花弁を1〜2つをティーポットに入れ、熱湯を注ぎ、蓋をして抽出する。3〜5分位置いてから飲む。酸味が有り、透明感の有る赤色の美しい御茶で、カフェインも無く、体調に合わせティータイムが楽しめる。
セージ(Sage) 和名=薬用サルビア シソ科。
サルビアの様なピンクや白色の花を穂状に咲かせる。耐寒性も有り、強くて育て易いハーブ。5〜7月に開花し、花の少無い季節の庭を彩る。
「死から救う」と言うラテン語が語源のセージ。其の威力は全世界に知られて居る。「庭にセージを植えて居る物は死な無い」とはアラビアの諺。イギリスでは「長生きしたければ5月にセージを食べろ」と言われ、五感を元気付ける為にフランスではセージは悲しみを和らげるハーブとされて居る。セージが此程に大切にされるのは、ピネン、シネオール、タンニン等の成分が様々な病気を防いでくれる為。濃い茶をリンスにすると白髪予防剤に。ソーセージ等の肉料理に加えれば、肉の臭みを取り脂肪分を分解してくれる。
【利用部位と薬効】
花、葉を食用、薬用、クラフトに利用。薬効は万能で、防腐、抗菌、抗酸化、抗炎症、精神安定、多汗症改善、老化防止、美肌、歯を白くする他、痛風、リウマチ、過労にも。
【症状別処方】
<長寿薬>
6〜7㎝に切った生の枝2〜3本は、水洗いの後水気を取って瓶に入れる。湯煎で約70℃に温めた蜂蜜200〜300㏄を注ぎ入れ、蓋をして保存。一週間〜10日後にセージを取り出す。此のエキス小匙1杯を湯で薄め、毎日飲む。
<嗽薬>
殺菌効果の高いセージは嗽薬にぴったりです。風邪の予防だけで無く、喉の痛みも和らげてくれます。
材料
セージ(又は、乾燥)生葉なら5枚、乾燥なら小匙1杯、水200㏄、蜂蜜小匙1杯。
①セージの葉に涌かし立ての熱湯を注ぎ、6〜7分ポット等で蒸らして濃い目のハーブ茶を作る。
②①のハーブ茶を濾して、蜂蜜を加え、冷ます。
【料理】
<セージの天麩羅>
薬効丸ごと取れるセージの天麩羅は、普通の天麩羅と同じ要領で、葉の両面に薄く衣を付けて、160℃位の油(オリーブ油でも良い)でカラリと揚げる。予め衣に塩を混ぜるか、揚げ立てに塩を付けて食べる。薩摩芋の薄切り2枚で、挟み揚げにするのも美味で有る。
<セージワイン>
抗酸化作用が肉料理に向く。
鍋に赤ワイン1本を入れ、弱火に掛ける。ワインが沸騰する前にセージ1枝を入れ火を止める。15分位経ってからセージを取り出し、紙フィルター等で濾してから瓶へ移す。冷蔵庫で冷やして飲む。
【生活】
<疲労回復セージ風呂>
乾燥セージ、ローズマリー、タイムを、4:3:3の割合で総量が約1/2カップに成る様ブレンドする。ガーゼ等の袋に入れて口を縛り、水の内からバスタブに入れてじっくりと抽出する。給湯式の場合は、予め鍋で煮出した物を加える。
【育て方】
種が割と大粒な為に、発芽し易く、育て易いハーブの1つです。種蒔きは八重桜の咲く頃。アルカリ性で、水捌けの良い場所を好む。香りが強いせいか、虫も付か無い。挿し木でも増やす事が出来る。
葉は銀色掛かった緑色をして居て布の様な手触りです。此は葉の表面に細かい毛がびっしり生えて居るから。此が水を含んで梅雨時には蒸れ易いので、葉っぱが混み合って来たら、枝を透かして、風通しを良くして上げる。
保存用の収穫は花が開花する直前に行う。耐寒性も有る多年草なので、一度植えたら毎年楽しむ事が出来る。
5年を目処に挿し木等して、新しい株に更新する。
アロエ(Aloe) 和名=キダチアロエ ユリ科。
サボテンの様な刺を持つ厚い葉が特徴で有る。其の種類は300以上有り、大きさ、形は様々。昼間は太陽に十分当てて、寒い夜は室内に入れて育てる。
今でこそ、アロエの美肌作用は広く知られて居るが、歴史上に其の作用を残したのは絶世の美女クレオパトラ。クレオパトラは其の美しさを保つ為、アロエの液を塗って居たと伝えられて居る。其の秘密は葉肉に含まれる成分。保水性に優れ、肌に柔軟性を与えるムチンや、美白効果が有り、染み、雀斑を薄くすると言うアロイン等、優れた成分を沢山持って居る。ビタミン等も多く含まれるので、美容効果は抜群で有る。又、「医者要らず」と言う異名が示す通り、便秘や胃腸病に効果を発揮する。皮を剥かずに服用すると薬効が高く成る。
【利用部位と薬効】
葉の刺を取って、其の儘食べれば、便秘、下痢、胃弱等に効果が有る。葉肉の部分は、面皰や切り傷、火傷に効果が有り、其の儘、若しくは擂り卸して使う。
【症状別処方】
<腹を綺麗にするアロエジュース>
便秘が続くと、吹き出物が多く成るので、アロエの力で身体の中から肌対策をする。
①アロエの葉3〜4㎝、蜂蜜大匙1杯、水1/2カップ、檸檬汁を準備する。
②アロエの葉は、綺麗に洗った後、刺を残さず取り去ります。
③皮ごと葉を擂り卸し、水と蜂蜜、檸檬汁を加え混ぜ合わせる。
<日焼けした肌を整えるアロエ葉肉>
①アロエの葉を10㎝程切り取り、緑色の皮を取り外す。
②日焼けしてヒリヒリする部分に葉肉を擦り付け、アロエエキスを塗り込む。
※肌の弱い人は、葉肉の絞り汁を水で薄め、コットンでパッティングする。
<肌すべすべアロエ化粧水>
アロエの生葉1/2本をしっかり洗って刺を綺麗に取る。皮ごと卸し金で擂り卸し、2重にしたガーゼ等で濾して出来上がり。此を2〜3倍程度の水で薄めて使う。保存が利か無いので作り置きは出来無い。冷蔵庫で保存して3〜4日が限度です。
※耳の後や肘関節の内側に付けて見て、炎症を起こさ無いかどうか調べてから使う様にする。
【料理】
<甘いアロエジャムで美肌対策>
①アロエの葉200gと檸檬汁大匙2杯、果糖25gを準備する。
②アロエは洗って刺を抜き、輪切りにする。
③材料を鍋に入れ、強火で煮込む。沸騰したらとろ火にして10分程度煮詰め、とろみが出たら火から下ろす。
美容
1.納豆は、腸内の異常発行を抑制し、血液を清める効が有るので、常食すれば美肌と成る。
2.鳩麦を日常摂っていれば効が有る。
3.胡瓜水は美顔料として有効で有る。化粧水として朝夕用いていると、色を白くし、日焼けを防ぎ、木目を細くするだけで無く、面皰、雀斑(ソバカス)を除く効果が有り、又、化粧下に用いても、化粧の乗りを良くする。
4.とまとは便通を調え、脂肪の消化作用が有り、栄養素を豊富に含有しているので、便秘や美肌に効き、脂肪太りを解消し、疲労を回復する。又、皮膚に適度な水分を与え、潤いの有る肌にする。とまとの汁で洗顔すると肌が奇麗に成る。
5.蓮根は末梢への血行を盛んにするので、皮膚の新陳代謝を良くし、吹き出物や皺(シワ)が取れ、皮膚に張りが出る。副食物として常食する事で有る。
6.海胆は体を温め、酵素やミネラルやビタミンをたっぷり含んでいるので、皮膚が美しく成り、女性にとっては絶好の食品で有る。
7.ローヤルゼリーは働き蜂の咽喉腺から分泌する乳状物で、此を少量ずつ、蜂蜜に溶かして飲むと、病気に対する抵抗力を増し、美容や強壮効果をもたらす。
8.椿の花に含まれる糖類に、滋養、強壮の効果が有るので、健康茶として続ける。
9.ピーマンを食べる。特有の辛味や香りが食欲を増す。カロチンやビタミンC、D等の作用で細胞の代謝が活発に成り、皮膚の染みや雀斑(ソバカス)が除去され、毛髪の艶が良く成り、又、霜焼けや皮下出血を防ぐ。
10.どくだみの全草の陰干しを煎じて飲む。
美肌
1.無花果の干した葉を浴湯料として、布袋に入れて使う。皮膚が滑らかに成る。
2.キャベツの生葉を良く噛んで食べる。キャベツに含まれて居るクエン酸、コハク酸、リンゴ酸等の有機が消化酵素に作用して老廃物の分解が促進され、血液の浄化に因って腸内の異常発酵を防止し、肝臓機能も強化されるので美肌効果を高める。
3.セロリージュースを作って飲む。
4.豆乳を飲む。
5.鳩麦を煎じ、御茶代わりに飲む。
6.鳩麦粥を作って食べる。
7.糸瓜水を塗る。
8.菠薐草を食べる。ビタミンAを豊富に含んで居るので皮膚の抵抗力を強化する。肌荒れや面皰(ニキビ)を無くし、奇麗な肌にする。
9.蓮華草を開花期に全草を刈り取り、陰干しにした物を御茶代わりに飲む。
10.乾燥した蓮華草の全草を適当に刻んで布袋に半分程入れ、鍋で煮詰めて袋ごと煮汁と共に風呂に入れる。
11.葡萄を種子ごと食べる。皮膚の角質化、全身細胞の苦返りに効く。
12.唐芥子黒胡麻黒酢を調味料として使う。
13.どくだみの全草の陰干しを煎じて飲む。
14.烏瓜酒を飲む。
15.納豆を食べる。
16.大蒜風呂に入る。
「身体の浄化と回復」のビームライトバーコードと同時に使用されると効果的です。
美肌(面長用)のビームライトバーコード(2000.2.11.UP)
※面長の顔に頬がふっくらする。
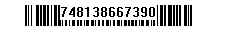
美肌(丸顔用)のビームライトバーコード(2000.2.11.UP)
※丸顔に頬がスッキリする。
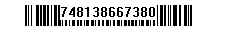
<ビームライトバーコードに関しての注意事項は3月17日を再度御読み下さい。>
6月24日
髪の毛
毛や爪は切っても痛く無い。此は死んで居るからだと言われて居る。又、一晩で真っ白に成ったとか、一週間で急に白髪に成ったとか言う事を聞く。特に、憂いや悲しみ、痛み、心配は強く作用する様にも見えるし、又、世間では昔からそう言われて居る。もし、毛が完全に死んだ代物で有れば、一週間やそこらで目立つ程白く成る物では無い筈だ。髪の毛は一日に平均0.3〜0.4㎜ずつ位皮膚の外に押し出されるので有って、一週間だと精々2〜3㎜伸びるだけで有る。皮膚の外に出た毛が代謝を行って居無いとすれば、例え、白く成るにしても一週間で皮膚から2〜3㎜の所だけが白く成る筈で有る。が、或る毛は一週間に数㎝の先迄も白く成って仕舞うと言うのは、生きて居る証拠では無いだろうか?
日本人の髪の毛は、真っ黒が絶対多数で、黒褐色が次に多い。そして、一般に女子因り男子の方が濃い。此の毛の黒さは、メラニンと言う色素の多寡に因って決まる。即ち、メラニンが多いと黒髪に、少無いと金髪に、メラニンが全く無ければ白髪に成る。白く成る原因は、毛の栄養が悪く成ってメラニンを作る酵素が減り、毛の中に細かい気泡が出来る為で有る。然し、気泡は外から入ったのでは無く、過酸化水素が分解して出来た炭酸ガスなので有る。
其の白髪は遺伝する物も有るが、長年住む環境(食物と水)にも影響されると考えられる。此を裏付ける様に、数年以上も欧米に住んだり、特に、幼少時代から住んで居ると、黒髪も褐色を帯びて来る人が居るし、母親が妊娠以前から妊婦時に肉食を主として摂ると、生まれて来る子供の髪の毛は褐色を帯びた髪の毛に成り、其の肉食量が多いと部分、又は、大部分が金髪に成る。又、若い時から海藻を沢山食べるとか、玄米御飯や麦御飯に根菜を摂って、太陽光線に良く当たると白髪が予防出来ると言う。だが、精神的影響も強く受ける。
髪の毛には、直毛、波状毛、糸球毛が有る。黄色人種は直毛が多い。アフリカの黒色人種等に見られる縮れ毛は、脳味噌を熱帯の直射日光から守る役をして居ると言われる。縮れた髪は、空気をたっぷり含んで居るので、断熱効果が大きい。
頭髪と身体の他の部分の毛の色とは必ずしも一致しない。頭髪が黒くても眉毛、髭、鼻毛は白とか、逆に、頭髪が白くて眉毛が黒いとか様々で有る。又、毛の色は加齢と共に部分に因って異成って来るが、其れと、全身の健康状態や生殖能力とは一般的に一致しない。極端な栄養不良とか、精神的ストレスの場合は別として。
髪の毛が薄く成るか、全く消えて仕舞ったのを禿頭(禿)と言う。医学では禿頭病、或いは、脱毛症共言う。が、脱毛症の方が意味が広い。禿頭病の原因には色々有る。唯、所謂男性の禿は98%が男性ホルモン(アンドロゲン)の生産過剰だと言われて居る。其の結果、頭皮の特に前頭や頭頂部分の組織(帽状腱膜)が厚く成り、根毛への血液の流れが妨げられるので禿に成る訳で有る。
髭や胸毛はアンドロゲンにより発育が促進される。従って、一日に2〜3回逆立ちしたり、マッサージしたりして頭皮の血液循環を良くする事が禿の予防や治療に成る。又、髪の毛は櫛で手入れする因りも、ブラシで手入れする方が良いと言う。其れに因って禿を治した人が多い。
食事は、肉食、砂糖、精製塩、人工添加物、酸化した油(何度も使用した食用油、油菓子等)、アルコール等が特に行け無い。
禿頭(トクトウ)治療用スープの作り方
薬効=発毛作用、回春作用、強精作用、血圧安定、頭皮に栄養を送る作用、便秘解消作用、精神安定作用、造血作用。
何首烏(カシュウ)、大棗、黄耆各38gを合わせ、茶の様に朝晩の空腹時に飲む。一日量。但し、始めの20日間は毎日飲み、後は一日置きに服用する。
可首烏は古代中国の伝説で、何(カ)老人が飲んで烏の濡れ羽色に頭髪が蘇り、生殖能力が壮者を凌ぐ有様に成った蔓どくだみの根塊で有る。大陸漢方の殆どの回春剤、発毛剤に配合される。大棗は棗果実で天然の総合ビタミン剤。黄耆は、きばおうぎの根で強精食(薬)に使う。血圧安定と頭皮に栄養を送る目的で此の茶に加える。三者共に便秘を防ぎ精神不安を鎮め、血を補う。
序でに、赤唐辛子と千振同量をアルコールに浸け、其れを、カット綿に浸して頭皮に擦り込む。希望は更に芽生えて来る
円形脱毛症、パーマ脱毛症
1.生姜汁を塗る。但し若禿や老人性脱毛には効か無い。
2.黒胡麻黒酢を地肌に擂り込む様に付ける。
「身体の浄化と回復」のビームライトバーコードと同時に使用されると効果的です。
育毛のビームライトバーコード(頭髪)(1999.9.30.UP)

<ビームライトバーコードに関しての注意事項は3月17日を再度御読み下さい。>
6月23日
聖天仁大神からの霊流とビームライトエネルギーを増幅する為のビームライトバーコードです。ビームライトバーコードを身に付ける時には、此のビームライトバーコードも同時に使用されるとビームライトエネルギーは加速し増幅されます。
加速のビームライトバーコード(聖天仁霊流とビームライトエネルギーの加速)(1999.8.26.UP)
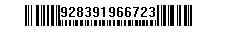
<ビームライトバーコードに関しての注意事項は3月17日を再度御読み下さい。>
6月22日
神経痛
神経とは神の道と書くが、其の神経は油で構成されて居る。痛みは流れが滞った酸欠状態に因って起こる。油の酸化で有る。手当法で述べて居るがどくだみ湿布と石鹸湿布が対症療法では特効で有る。
身体で痛みの感覚が起こるのは、全て知覚神経が刺激された場合で有る。だから、痛みは全て神経痛と言える。しかし、病名として一般に神経痛と言われて居るのは、次の様な条件を備えた物で有る。
①痛みの原因と成る様な客観的症状が見当たら無い。
②痛みは知覚神経の走路に沿って発生し、其の内特定の点は押すと非常な痛みが在る(圧痛点)。
③痛みは起きたり鎮まったりする。
結局原因が明らかで無い痛みが「何々神経痛」と診断される事が多い。原因が明らかに成ると、其処から独立させ、別の病気として扱う様に成る。将来医学の進歩に因って神経痛と言う病気は使われ無く成るだろうと言われて居るのも其の為で有る。
神経痛と似た症状を示すのは、筋肉痛、脊髄障害、ヒステリー等。筋肉痛は痛みが神経の走路に一致せず、痛みが持続的で有る点、脊髄障害は、極初期の頃は殆ど区別が付けられ無いが、直ぐに特有な症状が現れて来る点、又、ヒステリーに於ける痛みは、神経の走路や分布等解剖学的関連を無視した現れ方をする点等で、其其神経痛と区別出来る。又、1つの神経系で無く、身体の彼方此方が痛む場合としては、蛋白変性が主因に成って居るリュウマチか、で無ければ神経細胞の変性が選択的に起こる多発神経炎で、病気の性質は少し違って来る。とは言え、以上の様に分類に其程拘る必要は無い。何れにしても「神経痛の症状」から脱却を図る事が、治療法の眼目に成る。
痛みは神経の末端が刺激される事に因って発生する。詰まり、炎症、圧迫、牽引、更に発病物質の作用等の刺激が加わる訳だが、其れ等の刺激を生み出す直接的原因は色々で有る。例えば、組織の老化に因る変性、寒冷等に因るアレルギー反応、更年期障害等の内分泌機能失調、精神的ストレスに因る刺激物の産生等。又、最近は、血管の異常収縮や血流障害等、血管系の障害も重大な要素に成って居る。問題は何故其の様な組織や内分泌、血管等の障害が引き起こされるに至ったかで有る。其れは、血液性状が混乱して、組織細胞の新陳代謝が正常に行われ無く成ったからだ。兎も角、神経の末端に加えられた刺激は、神経繊維を伝わって脳に行き、其処で始めて痛みの感覚が起きる、実際に痛みを感ずるのは脳で有る。其れが、障害の起こって居る部位に感じられるのは、投射と言う神経特有の作用に因る物で有る。又、痛みの程度は、必ずしも其の儘障害の強弱を現す物では無い。我々の身体には、体質に因る感受性の違いが有り、精神作用に因る感情の色付けが成される。従って、神経痛の苦しみはなかなか解って貰え無い物で有るし、又、焦りや恐怖心等の為に、自ら痛みを倍増させて居る場合も有る訳で有る。
何れにしても、余り激しい痛みを持続させると、血圧上昇、胃炎、自律神経失調等の障害も起こり易いので、因り自然な方法で、痛みを和らげる事も必要で有る。ビームライト治療、全身骨格治療等を行うと高効果を得る。
だが、単に痛みを取るだけでは完全では無い。元々痛みは、病気と言う結果で有り、生理機能に歪みが生じて居る事の警報で有る。此の警報に因って、我々の身体は、早急に防衛体制を取る。身体自身が、歪みを是正しようとする。だから、其れに合わせて早めに適当な処置を取れば大事に至ら無くても済む。
極稀だが、生まれ付き痛みの感覚を全く持って居無い人が有る。其の様な人は、体内的な痛みの発生も無い訳だから、防衛力も弱く、おそらく短命に終わる。ともあれ、痛みの感覚が起こり放しに成って居るのは、生理機能の障害がずーっと存在して居ると言う事で有る。警報機を目の敵にするのは、筋違いで有る。
痛み其の物は局所に起こって居ても、生理機能障害は全て本質的には全身的な物で有る。体質を改善して、生理機能を正常化する事に因って、痛みが起こら無く成る状態にする事が根本療法で有る。其の為には、正しい食生活をする事が大切で有る。其の食事の玄米菜食の原則から懸け離れる程、生理機能の歪みは大きく成る。其の歪みが、神経痛の姿と成って現れ易いのは、特に、過食、白米や白パンの常食、動物性蛋白質食品の多食、精製塩や化学調味料の常用をして居る場合で、此等有害食品を避けなければ成ら無い。
玄米菜食に於いて、特に積極的に活用したいのが、梅干し、海藻類、胚芽食品、酵素、葱類、青野菜、植物油、純粋米酢、根菜類、蜆、牡蠣、海鼠等。此等は、カルシウム、ビタミンB・D・E・K、クエン酸、其の他の有機酸等の有効成分が補給出来る食品、及び、体力強化、保温、血液浄化作用の大きい食品で有る。桑の枝を細かく刻み、乾燥蓬を一日15gずつ煎じて飲む。薬草茶として、鳩麦、どくだみ、波布草、蓬を煎じた物を茶代わりに適宜飲む。又、木の実類や胚芽油等を摂ると、ビタミンE、リノール酸等に因って、神経細胞の代謝を正常にし、痛みを鎮める。
神経痛
1.鳩麦を粉末にした物と、糯米の粉末を混ぜて、白湯でクリーム状とし、此に薄い塩
味を付けた物を食べていると、自然に治る。
2.味噌汁や煮ころがしを作る時に剥いた里芋の皮は、神経痛の妙薬。煎じ詰めて毎食
後に飲むと効が有る。
3.蓬の葉と茎を布の袋に入れ、浴槽に浮かせて沸かすと良く温まる。風呂上がりに煎
じ汁を飲めば、一層効果が有る。
4.石榴の実1個を皮ごと輪切りにして、甘みを付ける為に甘草を適宜に加え、二合の
水で良く煎じて飲む。但し、かなり長期間続ける事。
5.枇杷の葉30〜40枚を細かく刻んで器に入れ、上質の焼酎を二カップ位注ぎ入れ、
一ケ月以上熟成させてから、濾過紙で漉す。此の枇杷葉酒で湿布すると、打ち身、腫れ
物等にも著効が有る。
6.生きた侭の泥鰌を擂り潰し、黒砂糖を泥鰌の量の三割か四割位入れて練り混ぜ、和
紙に伸ばして患部に貼る。
7.伊勢海老の殻と梔子(クチナシ)の実を、其其黒焼きにして混ぜ合わせ、此を一日一
回、4〜5gずつ白湯で服用し、毎日続けていると驚くべき卓効が有る。
8.一日に50mlの酢を、三回に分けて毎食後飲むと効が有る。水、又は、湯で薄めて
飲んでも良い。
9.大根卸しを痛む患部に貼ると効果大で有る。
10.生姜の搾り汁に少量の小麦粉と水を混ぜて練った物を紙に伸ばし、痛む所に貼って、
乾けば貼り換えていると、痛みも熱も取れて楽に成る。
11.松脂の粉末を水で飲む。
12.青木の葉茎の干した物を浴用として使用すると体を暖め、痛みを和らげる。
13.浅葱(アサツキ)の葉、白根を細かく刻み、陳生姜や山葵、又は芹、春菊の生汁を少
々加え、御つゆに入れて煮立て、熱いうちに飲み、休養を取る。
14.乾燥した浅葱を適当に刻んで煎じて飲む。
15.薊(アザミ)の乾燥した根を煎じて飲む。
16.苺の花期の葉、茎を乾燥し、煎じて温服する。
17.無果花の干した葉を浴湯料として、布袋に入れて使う。
18.独活の乾燥させた根を煎じて飲む。
19.梅干しの肉を日本酒で溶いて患部に貼る。
20.キャベツの葉をアイロンでしんなりさせて、患部に何枚が当てる。一日に2回位交
換する。
21.桑の細断した枝を煎じて飲む。
22.石榴の果皮を乾燥させ、此を刻んだ物を一日量3g煎じて3回に分服する。
23.乾燥させた里芋の皮を煎じて飲む。
24.春菊の葉、茎を乾燥して布袋に入れ、浴剤にする。
25.生姜油を患部に擦り込む。
26.白樺の細断した葉、樹皮を煎じて飲む。
27.白樺の細断した葉、樹皮を煎じて其の汁で患部を温湿布する。
28.杉菜茶を作って、御茶代わりに飲む。
29.芹料理を作って食べる。
30.芹ジュース(青汁)を作って飲む。
31.芹を適当に刻んで乾燥させた物を布袋に入れ、浴剤として使う。
32.どくだみの陰干しした葉を煎じて飲む。
33.目弾き(益母草:ヤクモソウ)の干した茎葉、根の上の方10gを毎日煎服する。
34.大蒜の生汁に胡麻油を混ぜて患部に塗る。
35.鳩麦を煎じ、御茶代わりに飲む。
36.鳩麦粥を作って食べる。
37.糸瓜水を温めて飲む。
38.蜜柑風呂に入る(皮を刻んで乾かし、保存して置いた物を布袋に入れ浴剤として使
う)。
39.八手の乾燥した葉を刻み、布袋に入れて入浴する。体が温まり痛みが和らぐ。
40.蓬茶を作って飲む。
41.蓬青汁を飲む。
42.蓬エキスを飲む。
43.山葵卸しを布に伸ばして患部に貼り、乾いたら取り替える。皮膚の弱い人は、小麦
粉を混ぜ、薄めて貼るか、皮膚に食用油を塗って用いる。
44.南天の葉を包丁の峰で少し叩いて患部に貼り付ける。
45.コンフリーを食べる。より強い薬効を求めるなら根が良い。陰干しの粉末、金平、
天麩羅等で食べる。
46.石蕗(ツワブキ)の生葉の揉み汁をガーゼ等に浸し、患部周辺を湿布する。
47.木天蓼(マタタビ)の果実の塩漬け、蜂蜜漬け、焼酎漬けを食べる。
48.木天蓼の葉、茎、実全部を風呂に入れる。
49.木天蓼の葉、茎、実全部の濃厚搾り液で患部を浸したり、塗布する。
50.零会子(ムカゴ)を軽く潰して酢に浸けて貼る。零会子が乾いたら貼り替える。
51.鳴子百合の花、葉、茎、全草を採取し、葉は御浸し。花は御茶に浮かせて飲む。茎
は干して御茶を作る。浄血作用が強い。
52.紅花の干した花を煎じて飲み、飲用後は風呂に入れる。
53.殻付きの鳩麦を一掴み水に浸けて置く。此を鳩麦と一緒に同量の豚肉と葛根を半日
とろ火に掛けて濃縮スープを作る。
54.亀料理を食べる。
顔面神経痛
1.陳生姜約60gを卸して木綿の袋に入れ、約一升の熱めの湯の中で振り出して、此の生姜湯で患部を何度も罨法して、良く温める。
2.石蕗(ツワブキ)の生葉の揉み汁をガーゼ等に浸し、患部周辺を湿布する。
3.木天蓼(マタタビ)の葉、茎、実全部を風呂に入れる。
4.木天蓼の葉、茎、実全部の濃厚搾り液で患部を浸したり、塗布する。
5.零会子(ムカゴ)を軽く潰して酢に浸けて貼る。零会子が乾いたら貼り替える。
6.鳴子百合の花、葉、茎、全草を採取し、葉は御浸し。花は御茶に浮かせて飲む。茎は干して御茶を作る。浄血作用が強い。
7.目弾き(益母草:ヤクモソウ)の干した茎葉、根の上の方10gを毎日煎服する。
8.どくだみの全草の陰干しを煎じて飲む。
9.紅花の干した花を煎じて飲み、飲用後は風呂に入れる。
10.殻付きの鳩麦を一掴み水に浸けて置く。此を鳩麦と一緒に同量の豚肉と葛根を半日とろ火に掛けて濃縮スープを作る。
11.松脂の粉末を水で飲む。
12.亀料理を食べる。
三叉神経痛
或る日突然、瞼や目尻、上顎から小鼻、口元等に針で刺された様な痛みが走る。三叉神経痛の始まりで有る。痛みは徐々に発作の様に繰り返す。そして、風が当たっただけでも耐え難い激痛に成る。原因の80〜90%は動脈硬化に因り顔筋肉が酸欠状態に成り、筋肉が硬化して神経を圧迫してしまう為だ。残りの20〜10%は腫瘍や動脈瘤に因り神経を圧迫する。
身体の警告として、
①突然、顔に針を刺された様な痛みが走る事が有る。
②①の痛みが繰り返して起きる様に成り、痛みも耐え難い。
③痛みは必ず顔面の片側だけ。
④痛みは長引かず、長くても2分以内で治まる。
⑤発作と発作の間には全く痛みが無い。
⑥小鼻や口の周り等をほんの少し触れただけで痛みが走る。
⑦風が触れただけでも耐え難い痛みが走る。
⑧食べ物を噛むと痛む。
⑨痛みが有る時は、話すのも困難。
⑩痛みの発作は何時も同じ形で起きる。
肋間神経痛
肋骨と肋骨の間、肋骨を走る神経が痛む此の病気は、圧迫される様な痛み、又は、鈍い痛みが短く発作的に起こる。第3と第4肋骨の間、第8と第9肋骨の間が痛む事が多い。
咳や嚔等、力んだ時に出易い。原因は、手術や怪我で胸椎が変位した場合が多いが、癌等の腫瘍が神経や骨に移転して居る場合も有る。稀にはウイルス感染が原因で有る事も有る。
身体の警告として、
①帯状疱疹の治療や、狭心症と言われた事が有る。
②嘗て胸部に怪我をしたり、開胸手術をした経験が有る。
③咳や嚔や排便なので力んだ時に痛みが起こる。
④肋骨に沿って指を押して行くと特に痛い。
⑤胸、又は、脇腹の片側に痛みが在る。
⑥横に成って居ても痛い。
座骨神経痛
1.蜜柑(陳皮)風呂に入る。
2.石蕗(ツワブキ)の生葉の揉み汁をガーゼ等に浸し、患部周辺を湿布する。
3.木天蓼(マタタビ)の葉、茎、実全部を風呂に入れる。
4.木天蓼の葉、茎、実全部の濃厚搾り液で患部を浸したり、塗布する。
5.零会子(ムカゴ)を軽く潰して酢に浸けて貼る。零会子が乾いたら貼り替える。
6.鳴子百合の花、葉、茎、全草を採取し、葉は御浸し。花は御茶に浮かせて飲む。茎は干して御茶を作る。浄血作用が強い。
7.目弾き(益母草:ヤクモソウ)の干した茎葉、根の上の方10gを毎日煎服する。
8.どくだみの全草の陰干しを煎じて飲む。
9.紅花の干した花を煎じて飲み、飲用後は風呂に入れる。
10.殻付きの鳩麦を一掴み水に浸けて置く。此を鳩麦と一緒に同量の豚肉と葛根を半日とろ火に掛けて濃縮スープを作る。
11.松脂の粉末を水で飲む。
12.亀料理を食べる。
6月19日
止血
有らゆる出血には胡麻塩とか蓬を使う。胡麻塩は頓服で。蓬は御茶で飲むか、切り傷等には葉を揉んで患部に当てる。又、蓬茶を飲む時に陳生姜を擂り卸して5g程入れて飲むと効果は加速する。柿の葉茶も同様に効果が有る。
包丁等で、切り傷をした時には砂糖か塩を傷口に乗せてギュッと圧力を掛けて遣れば止まる。又、馬油を塗るのも良い。
但し、血尿を止める時に塩気を入れると止まるが飛び上がる程痛い。此の場合はヤンノーや薄い玄米スープを大量に飲ませると良い。
普段、ビタミンK(納豆等に多い)を多く摂って居る人は止血し易い。又、玄米餅を食べると血液粘度が向上します。だから、蓬玄米餅を食べると体内の出血には非常に効果が有る。
「身体の浄化と回復」のビームライトバーコードと同時に使用されると効果的です。
止血のビームライトバーコード(1999.6.19.UP)

<ビームライトバーコードに関しての注意事項は3月17日を再度御読み下さい。>
6月18日
気触れ
気触れた時の痒みは理性を失って仕舞う程のものだが、先ずは患部を冷やすと耐え難い痒みも落ち付く。身体が熱を持って来るので、身体を冷やす根菜類のジュースを飲むと落ち付いて来ます。動物性蛋白質の摂取は駄目で有る。肝臓部位に乇草をミキサーで砕いた物を2㎝厚さ位に貼ると良い。野山等に出向いて漆気触れに成った時には枇杷種の焼酎漬けが有れば、其れを1,000倍以上に希釈して(50万倍〜100万倍の方が因り効果が有る)患部と肝臓部位に湿布すると特効が有る。
接触性皮膚炎(気触れ)
強い刺激物が直接皮膚に付いて炎症が起きるのが、刺激性皮膚炎。刺激物が皮膚を通過して体内に入り、アレルギー状態が出来た所へ再び刺激物が付いて湿疹が出来るのがアレルギー性皮膚炎で有る。
アレルギー性の場合症状が出るのに時間が掛かるので、原因物質を発見するのが非常に難しい。刺激性皮膚炎でも、家庭用の洗剤や化粧品等の弱い刺激が繰り返される場合、其の時の体調に因って、気触れたり気触れ無かったりする。此の場合にも原因究明には時間が掛かる。
気触れの原因は実に多い。金属、アクセサリー、皮革製品、医薬品、洗剤、ゴム、プラスチック、植物、果物等、身の回りの全てで有る。
身体の警告として、
①大人なのに汗疹が出来易い。
②蚊に刺された部分が赤く大きく腫れ上がって仕舞う。
漆気触れ
1.鰹節を煎じて飲むと治る。
2.蟹の煮汁を付ければ治る。
3.蟹を突き潰して其の汁を塗ると治る。
4.桔梗の生の茎、葉を搾って塗る。
5.桜の葉を刻み、布袋に入れた物を浴剤として、桜湯を沸かして入浴する。
6.枝下柳の葉、枝の煎じ汁で患部を湿布する。
7.枝下柳の葉、枝を揉んで布袋に入れて浴剤として使う。
8.栗の葉、毬(イガ)、渋皮、樹皮を濃く煎じて、其の汁を冷やして冷湿布する。炎症
が治まったら、軽くオリーヴ油か植物油を塗って於く。
9.栗の葉、毬(イガ)、渋皮、樹皮を濃く煎じて、其の汁を浴剤として使う。炎症が治
まったら、軽くオリーヴ油か植物油を塗って於く。
10.栗の生葉を揉んで、患部に塗る。
気触れ
1.干し柿を煎じて熱いうちに飲む。
2.ぎしぎしの種子の煎じ汁で冷湿布をする。
3.山椒の果皮の煎じ汁を患部に塗る。
4.垣通し(カキドウシ)の葉を風呂に入れる。
5.黄蘗(キハダ)の幹の皮を剥くと、真黄色の内皮が有る。其れを白に干して粉末にし、
患部に擦り込む。胡麻油で練ると使い易い。外性器の気触れの特効薬で有る。
6月16日
浮腫(心臓病・腎臓病)
心筋梗塞は、栄養過多で起こる慢性病で有るが、長く煩うと心不全に陥り、浮腫が生じる。心筋梗塞以外の心臓病や腎臓病でも浮腫は付き物で有る。
浮腫は水分其の物で有るから「冷・水・痛」の三角関係から考えても、完全に「水・冷」に因る陰性の病気で有る。身体を温める陽性食品をしっかり食べ、排尿(利尿)を促す様な食物を摂ると良い。
<治療>
①小豆は利尿作用が強力なので、玄米に小豆を1〜2割入れて赤飯にして食べる。又、茹で小豆や小豆昆布を食べる。
②玉蜀黍の毛を陰干しにし、水の量が半分位に成る迄煎じて飲む。
③浮腫も酷く、動悸、息切れも伴い、心臓の機能が可成り落ちて居る人は、卵醤を飲むと良い。
④西瓜は利尿作用が有るが、夏だけの物。然も、身体を冷やす作用も有るので、冷え症の傾向の有る人は、自然塩を振り掛けて食べると良い。又は、西瓜糖を作り冷蔵庫に保存し、適宜利用すると良い。
利尿
1.小豆の煮汁には尿を通じる効が有る。毎日飲む様にすると良い。塩を入れず、砂糖を少々入れると効果が大きい。
2.小豆と昆布を一緒に煮て食べる。
3.尿が詰まったり、尿の出が悪い人等には、鯊(ハゼ)を水煮にして(薄い塩味を付けると飲み易い)、其の煮汁を飲むと効が有る。勿論、鯊も食べる。
4.桑の根皮(根を3日程水に漬けた後、表皮を剥ぎ、コルク層を除いて内皮を取る。白色で甘みの有る物が良品とされて居る)を刻んで煎じて飲む。
5.朝顔の粉末状にした種子を1回分、ほぼ耳掻き1杯(0.3g)を水で飲む。
※効き目が強いので、病後の人や妊婦は乱用し無い事。
6.薊(アザミ)の乾燥した根を煎じて飲む。
7.葦の乾燥した根茎を煎服する。
8.喉の渇き、尿の出の少無い人は、其の原因と成る病気を治さ無ければ成ら無いが、一方、止渇や利尿の作用の有る竹の子を薄味に煮たり、竹筍湯(竹の子スープ)にして食べると効果が有る。
9.アスパラガスを茹でて食べる。
10.アスパラガスの青汁を作って飲む。
11.アスパラガスを生の侭適当に刻んで乾燥させた物を煎じて飲む。
12.乾燥した浮草と繁縷(ハコベ)を等分量煎じて飲む。
13.靫草(ウツボグサ)の花穂、葉、茎を煎じて飲む。車前草、どくだみを加えると因り効果的で有る。
14.夏、車前草の花穂の出た頃全草を陰干しにして、車前草茶を作って飲む。
15.花梨の果実を輪切りにして乾燥し、適当に刻んで煎じて飲む。
16.河原蓬の花穂と種子を煎じて温服する。
17.蒟蒻料理を色々工夫して食べる。
18.桜ん坊の実の柄を適当に刻んで日陰で良く干して、此を煎じて飲む。
19.西瓜の乾燥した皮や種子を煎じて飲む。
20.西瓜糖を一日3回、小匙1〜2杯飲む。
21.山椒の種子10gを400㏄の水で半量に煎じて服用する。
22.杉菜茶を作って、御茶代わりに飲む。
23.芹料理を作って食べる。
24.芹ジュース(青汁)を作って飲む。
25.芹茶を作って常用する。
26.蒲公英の乾燥した根に花、葉、茎を加え、煎じて温服する。
27.蒲公英茶を作って適時に常用する。
28.茅(チガヤ)の根と小豆を等量を煎じて飲む。
29.露草の全草を煎じて飲む。
30.乾燥した玉蜀黍の毛を煎じて飲む。
31.玉蜀黍の毛に、波布草、車前草等を加えて御茶代わりに飲む。
32.乾燥した木賊(トクサ)を煎じて飲む。
33.茄子の花を陰干しにして煎じ、其の汁を飲む。
34.薺(ナズナ)の葉、茎を煎じて飲む。
35.繁縷(ハコベ)の乾燥させた全草を煎じて御茶代わりに飲む。
36.糸瓜の未熟果を刻んで乾燥し、煎じて飲む。
37.糸瓜の種子の黒焼きを一日3回に分けて飲む。
38.包の木の樹皮を煎じて飲む。
39.茗荷の根を煎じて飲む。
40.メロンを其の侭生食する。
41.林檎の果実を皮ごと輪切りにし、陰干しにして、煎じて御茶代わりに飲む。
42.蓮華草の乾燥した全草を煎じて飲む。
43.銀杏の実を一日10粒程生で半月続けて食べると、尿が良く出る様に成る。尿路感染症の患者には特に向いて居る。軽症ならば、銀杏の毒消し作用も手伝って、自然な尿道洗浄の結果排尿時の痛みが去り治って仕舞う。
※焼き銀杏は、尿が詰まって、尿閉気味の人は死の苦しみを味わうので、必ず生で食べる事。
44.豚の腎臓が良いが、膵臓ごと入手出来れば尚効果的で有る。刻んで、大蒜と生姜を擂り卸し、日本酒と醤油に漬けて食べる。
45.垣通し(カキドウシ)の陰干しを煎服する。抜群の利尿効果で有る。副作用が無い、気長な連用が骨で有る。
46.目薬の木の樹皮・小枝・葉を前じて飲む。
47.烏瓜酒を飲む。
48.青葛藤(アオツヅラフジ)を冬から春の彼岸迄に摂集して置き、髭根を除いて輪切にして天日で干し、煎じて飲む。息切れや動悸が鎮静し、尿が良く出て浮腫んだ全身が引き締まる。
49.柿の葉茶を飲む。
50.ギャバロン茶を一日3回飲む。
51.黒豆と小豆を同量ずつ混ぜて、焙烙等で良く炒った物を、水5に対して1の割合いで入れて煎じ、半量に成った物を御茶代わりに飲む。早ければ浮腫が4〜5日で取れる。
52.梅酢を10㎝四方の布にたっぷり湿らせて、夜の入浴後に貼る。
53.青木の葉を火に炙り2枚に剥がし、トロトロした方を臍に貼る。
54.胡瓜には強力な利尿作用が有るので、人参、林檎、緑黄野菜の基本ジュースに加えると良い。但し、胡瓜は身体を冷やす作用が有るので、冷え症の人や、遣って見て冷えの為利尿の効果が無い場合、胡瓜の漬け物や糠味噌にして多く食べる様にすると良い。
55.腹水が溜まる程の浮腫には、牛蒡、人参、林檎を基本に緑黄野菜を加えてジュースにして飲む。牛蒡は、包丁を入れたら直ぐにジュースにして灰汁が出る前に飲ま無ければ行け無い。
「身体の浄化と回復」のビームライトバーコードと同時に使用されると効果的です。
利尿のビームライトバーコード(1999.10.28.UP)
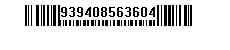
<ビームライトバーコードに関しての注意事項は3月17日を再度御読み下さい。>